「Art×多摩ニュータウン」 開発さん&水野さん
ふとしたきっかけから始まるアートと街のつながり
地域に入ってアートの力でできることを探したい
「“たまに塾”は基本的におせっかいなグループだと思います。頼まれてもいないのに、アートで何か役に立てることがないかを探しているんですから。でも、そんなグループがもっと増えていくと良いと感じています。」多摩センターエリアを舞台にアートプログラム“たまに塾”を主宰する開発さんはこう語る。“たまに塾”という活動をはじめようと思ったのは、多摩ニュータウンが少子高齢化という問題に直面しているというニュースを見たことがきっかけだという。「少子高齢化は今後の日本を考える上での重要なキーワードだと感じていましたので、実際に地域に入り現地の状況を知りながら、アートの力で何ができるのかを考えてみたいと思いました。」一般的にアートでまちおこしというと、自治体が外部のアーティストを呼ぶケースが多いのだが、“たまに塾”は地域の誰からも必要とされていない状況、つまりはおせっかいというかたちでスタートした。決まったテーマや帰着点があるわけではなく、「○○かもしれない」という想定のもと、アートの力でできることを探すことにしたのだという
コミュニケーションアートが出発点
開発さんは日常にあるものや出来事、関心などをモチーフとして、「コミュニケーション」をテーマにパフォーマンスやワークショップなどを展開、活躍するアーティストで、これまでも日本各地で地域に入り込んだプロジェクトを行ってきた。外の人間として地域の中に入ってそこに暮らす人たちと一緒に何かをすることで、「日常」が普段は味わうことのない「発見に満ちた時間や空間」になるのだという。多摩センターを舞台にした“たまに塾”の出発点もこの「コミュニケーション」というキーワードにある。
多摩センターエリアは故郷がしっかりと根付いている街
“たまに塾”では、多摩センターエリアの落合団地の住民の方々との座談会を重ねたり、周辺で街歩きワークショップやミーティングを行ったりと、リサーチ活動を続けてきた。実際に地域に入った開発さんの目に、多摩ニュータウンはどんな街に映ったのだろうか。「住民の皆さんと話をしてみるととても元気で前向きな印象でした。それぞれが地域につながりをつくり地元を愛し、問題があれば自分たちで解決するという意識が高かったように感じます。駅前の景色は一見、人工的で無機質に見える多摩センターですが、少し足を踏み入れると、40年という年月で生まれた故郷がしっかりと根付いている街だと思いました。」開発さんがニュースで聞いて最初に思い描いていたイメージとは全く異なり、良い意味でのズレを感じたという。
人と人のつながりを広げたい
多摩ニュータウンは団地が多い分、共有スペースが多い特徴がある。“たまに塾”の最近の活動ではこの共有スペース、特に「ベンチ」に着目した「青空会議」を開いているという。設置された時代により異なるデザインの様々なベンチを会議の場所としてみんなで集まり、ベンチの使い方にはじまり地域住民にとっての未来の街についてなど、色々なテーマで、世間話も交えながらゆっくりと語り合っている。この緩やかな会議は長いときでは5時間にも及ぶというから驚きだ。現在の「青空会議」は塾生だけで開いているが、今後はオープンな活動にして、人と人のつながりを広げていきたいと考えているそうだ。活動に参加している塾生の中には地域をよく知る落合団地の住人もいて、「何ができるのか」という視点で自分が住む街を見ることはとても新鮮で、日常では見過ごしがちなものに着目することでたくさんの小さな気づきがあるとのだという。地域の住人としてこのプロジェクトの可能性を実感している一面と言えよう。
この街に必要なのは漢方薬のようなプロジェクト
どちらかと言えば、外からやって来たアーティストは、ある瞬間や、出会った言葉を作品として作り上げていくことが多いそうだが、開発さんの“たまに塾”は今後もゆっくりと活動していきたいという。「多摩ニュータウンは僕の年齢と重なり、自分事のように感じられる存在なんです。人間が作り出した理想郷であるこの街がこれからどのように変わっていくのかはとても興味深いです。私もそろそろ再生しなくてはいけないかな。」微笑みながらそう語る開発さんは、ご自身と多摩ニュータウンの生い立ちと今後を重ね合わせながら街の観察を楽しんでいるようだ。
「この街に必要なアートプロジェクトを考えた場合、問題解決型やイベント型の何かを起こすようなプロジェクトではなく、場所や人を知りながら寄り添い、現状を維持するようなプロジェクトが良いのかもしれないと思っています。薬で例えるとしたら、抗生物質ではなく漢方薬のようなプロジェクトです。」コミュニケーションという視点で街をじっくりと観察する開発さんたちの活動はまさに処方箋のひとつとなるのだろう。「僕ができることは、小さな石を水面に投げ込むことくらいです。でも、それをきっかけにして多くの活動の輪がゆっくりと広がってくれたらいいなと思っています。」開発さんたちの出会い探しの活動はまだまだ続きそうだ。
多摩ニュータウンは街と緑のバランスが魅力
「多摩ニュータウンはとても明るくて緑が豊かなイメージです。それも都心のような半端な緑ではなく本当に豊かな緑。街と緑のバランスがとても良いと感じます。」水野さんはご自身が暮らす東京の下町と比較して、多摩ニュータウンの印象をこう語る。
水野さんは多摩市近隣の美術大学に通うデザイナーを志す学生で、多摩市が中心となり進めている「多摩ニュータウン再生プロジェクト」のロゴマーク制作を手がけた人物だ。幼少期から絵を描くことやものづくりが大好きだったという水野さん。進学した美術系高校で先生方や友人たちから受けた影響がとても大きく、より深く美術を学び美術に関わる仕事がしたいと自身の将来を決め、当然のごとく美術大学へと進んだそうだ。
「多摩ニュータウンの魅力である自然と街の調和のイメージを大切にしながら作りました。その上に、人や企業、学校などがひとつになって街が活性化していき、やがて大きな芽が出てくる様子を表現しました。」とロゴマークの特徴を明るい表情で語る水野さんだが、実は、これまで多摩ニュータウンは大学へと通う途中にある街という程度の認識で、あまり身近な存在ではなかったのだという。大学で紹介されたロゴマーク募集の案内がきっかけで多摩ニュータウンと急接近することになったわけだ。
街がもっと魅力を増していくきっかけに
ロゴマークのテーマが街の“再生”ということで、水野さんも当初は多摩ニュータウンに対して少なからずネガティブなイメージを抱いていた。ところが、制作の過程で多摩ニュータウンという街について詳しく調べたり地域を深く知る人々に実際に話を聞くことで、次第に街としての利便性と緑のバランスや人々の暮らしぶりが魅力であることを実感し、ロゴマーク制作で最も重要なイメージ作りも自然な流れで具体のものとなっていったという。「再生とは最盛期だった頃に戻すという意味ではなく、今ある魅力を活かしながらこれからの時代に合う街をデザインしていくことだと思いました。このロゴマークは、地域に住んでいる人たちにも気軽に使ってほしいですね。そして、多摩ニュータウンがこれからもっともっと魅力を増していくきっかけになったらうれしいです。」偶然とも言えるきっかけから始まった水野さんと多摩ニュータウンの関係だったが、若きデザイナーの卵も今では多摩ニュータウンのこれからに大きな期待を寄せる一人となった。
「とても元気があり、多摩ニュータウンの魅力と明るい将来イメージが一目で伝わるデザイン」とアーティストの開発さんもロゴマークを評価する。次の“たまに塾”の青空会議ではこのロゴマークがテーマとして登場するかもしれない。
アートと多摩ニュータウンのつながりから生まれた未来に向かう希望の芽は、地域の中で育まれ、やがて大きな木へと成長していくことだろう。
https://www.facebook.com/tamanijyuku
http://www.city.tama.lg.jp/plan/948/20048/021540.html
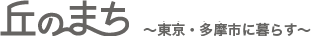




 開発好明さん
開発好明さん
 水野安奈さん
水野安奈さん


















































